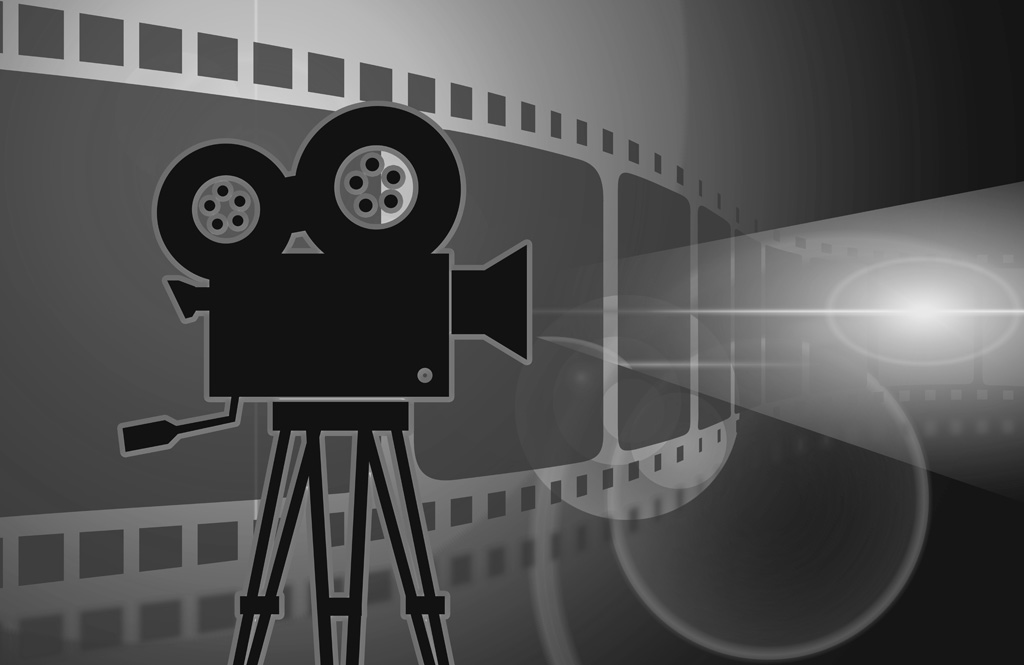題名:『バビロン』
製作国:アメリカ
監督:デイミアン・チャゼル監督
脚本:デイミアン・チャゼル
音楽:ジャスティン・ハーウィッツ
撮影:リヌス・サンドグレン
美術:フローレンシア・マーティン
公開年:2023年
製作年:2022年
目次
あらすじ
夢を抱いてハリウッドへやって来た青年マニーと、彼と意気投合した新進女優ネリー。サイレント映画で業界を牽引してきた大物ジャックとの出会いにより、彼らの運命は大きく動き出す。恐れ知らずで美しいネリーは多くの人々を魅了し、スターの階段を駆け上がっていく。やがて、トーキー映画の革命の波が業界に押し寄せ……。
引用元:
※以降ネタバレあり
これは"時代"が破壊する文化や人生とそこから芽吹き、新たに続いていく文化や人生への賛歌だ。
人は時代という大いなる流れを前に無力。だが、一個人同士が感情や肉体をぶつけ合い、一つの集合体へと至る時、そこに帯びる熱こそが時代の突き動かす燃料となるのは事実であり、本作はそんな時代の破壊と再生の連続こそが「映画なのだ」と肯定する。豪華絢爛、酒池肉林、死屍累々の時代を生きた者達の栄光と変化についていけなかった者達の破滅を一つの大きな"泡沫の夢"として、映画史の養分にしてしまう。
なんて残酷で、魅力的で、映画的。
映画史とはかくも残酷で、無数の屍を置き去りにすることで史を紡いでいるということを、熱量で以て体感させてくれる。
詳しく書いていく。
人こそが"背景"であり、時代こそが"前景"
まず本作は個人を描くより"時代"を描くことを最優先にした作品だということは理解する必要がある。時代とは本作にとって「映画史」と同義語である訳だが、"時代を優先した"とはつまり、人こそが"背景"であり、時代こそが"前景"であるという歪な形で作られた映画にあることだ。
それは『ラ・ラ・ランド』との比較で分かりやすく見えてくるだろう。デイミアン・チャゼルは映画愛、音楽愛の監督であり、本作に近い作品として『ラ・ラ・ランド』を監督している。二作は時代は違えど、郷愁で"黄金期の映画"を再び現代に呼び起こす試みで作られた作品だが、明らかに違うのは恋愛と映画史のバランスだ。
『ラ・ラ・ランド』はあくまで映画史(時代)は背景として機能しており、主軸として前景化されているのは主演二人の恋愛であった。映画史はそれ単体で描くことが不可能に近く(ドキュメンタリーになってしまうため)、それを媒介する被写体が必要である。チャゼルはそこに2人の夢追い人を被写体として用意し、彼らの夢想的な恋愛を媒介にしてかつての黄金期のミュージカルへの憧憬を表現した。多くの人にとって『ラ・ラ・ランド』は恋愛ミュージカルとして認識されているのも、恋愛が前景化した状態を保持したまま、映画史(ミュージカルそのもの)は背景として賛歌したからだ。
ただ今回はその恋愛と映画史の関係性が崩壊し、逆転している。多分それは意図的に隙間なく人を配置して群像劇として描くことで、個人を群像に埋没させているからだ。端的にいえば個人をモザイク画に敷き詰めているようなイメージだ。
パンフレットにも「有機的なグループ全体を一つの個として見ることを目指した」と書いてあるように、映画史という大きな"一"にフォーカスが常に合わされていて、個人(マニーやネリー、ジャック)はピンぼけな背景として、構成要素として意図的に配置している。それは映画序盤の屋敷で狂乱如きパーティの様子において、ひとつの集合体として撮影されたダンスシークエンスが象徴しており、人の集合体としての時代を描いてこうとしているのが分かる。
個人描写について、特にマニーとネリーの恋愛の求心力の低さは『ラ・ラ・ランド』を作った人間のものとは思えないものになっていて、20年代の熱狂と狂騒の映画をネリーに重ね、そこに漠然と憧れを抱く人としてマニーをシンクロさせることでようやく納得のいく描写になっていると思う。
ネリーを観るマニーという構図、ネリーと20年代の相関、そしてネリーの消えたクライマックスで闇→光→闇へと移動する様子とエリノアの「スポットライトの話」から行き着くその後も続いていく映画史への示唆も、その「ネリー=過ぎ去った20年代映画史」の構図を強化しているだろう。
そんな感じで、本作には多くの登場人物が存在するが、それらは時代を構成するピースでしかなく、その歪な描き方を選択しているのが本作だ。
それを踏まえて考えるとジャックとマニーの交流が後半でほとんどないのは勿体ない気もしている。
破壊と誕生の映画史を肯定する
時代を主人公とした本作は混沌の20年代(サイレント期)から秩序の30年代(トーキー期)への時代の移り変わりの中で何が破壊され、何が生まれたのかを終ぞ描く。
それはパーティーや撮影現場、映画館等の変化を通して描かれる。冒頭の狂乱の宴はブルジョア共の社交の場に変化し、荒野で木と帆布で作られた小型セットは鉄筋で構築された録音環境のある室内セットに変わる。サイレント期からトーキー期へと変貌し、映画館には歓声以外の"台詞"が響き渡る。
そういった時代の変化を絶え間なく本作は描き、変化によって破滅していく人々の姿を描くのだ。個人的にはやはりトーキーへと移り変わり、ネリーの絶対的な存在感が摩耗していく撮影シーンがお気に入り。コメディでありながらも、端的に当時の変化に翻弄される人々を描いており、ちゃんと尺を取る価値のある場面だと思った。
そういった時代の変化は置き去りされそうになっている人々にフォーカスされるが故に残酷に映る。時代に適応しようとする人々の苦悶の表情。特に黒人文化が注目されることで消費の対象にされるシドニーの姿には心痛めてしまう。
だが本作は"かつて"を良しとし、新しきを否定する映画にはなっていない。むしろその破壊と誕生のサイクルをその残酷さを理解した上で、肯定するのだ。それこそが「時代」であり、「映画史」なのだと。
映画史においても時代の変化と共に技術や文化が廃れ、新しいものにすげ替えられていく。デジタル化、SFX、VFX、3D、サブスクの定着…あらゆる観点であるゆる進化があり、その背景には忘却されていった者やモノが沢山ある。何かが生まれるということは何かが死ぬということ。誰か我スポットライトに当たるということは誰かがスポットライトに当たらないということ。
映画史において、それは20,30年代の移り変わりにだけでなく、それ以前にもそれ以降にも繰り返し繰り返し起こっていた。それはまさにラストの映画史のモンタージュで選出された作品群に表れている。ラストのモンタージュ映像ははっきりいってダサい。(マイブリッジから始める点は評価したいが)
それやるなら『ニューシネマパラダイス』をもう一回見直してこいとは思うし、そのサンプリングを映画愛とは言わない。
ただ、その前段階のマニーが『雨に唄えば』を通してかつての自身の生きた時代を「映画」にされたという事実に直面することで、映画史の傲慢さに再確認し、自分がその破壊と誕生のサイクルのように一ページであったことを理解し、マニーがスクリーンにもしかしたらネリーを見たかもしれないと思わせる演出にこそ、狂気的な映画愛を感じさせられるのだ。全く以てダサい映画のサンプリングと、感動的な一観客としてのマニーの描写、それを同居させるところにも本作の歪さを感じさせる。
確かに本作は野心的すぎかつ歪すぎて受けいれ難い作品になっているのは間違いない。賛否両論も分かる。ただ自分は、この挑戦と野心の一本が大好きだ。
演出について
最後は演出他について。本作はトム・クロス(編集)とジャスティン・ハーウィッツ(音楽)、デイミアン・チャゼル(監督)の密な共同作業により編集と音楽とカットが完璧に重なっていた点が最も特筆すべき点ではないだろうか。撮影開始前から音楽とショットのプレビスみたいなのを作成したり、撮影後も同じ空間で作業することで確認修正のサイクルを早くまわせたことが要因になっているようで、長回しから手持ちカメラのショット、細かいモンタージュによる緊張感の演出、全てが完璧にハマっていたと思う。
余談として、トビーマグワイヤが『ブギーナイツ』のアルフレッド・モリナのポジションにいるのも映画ファン的には面白いなと感じた。